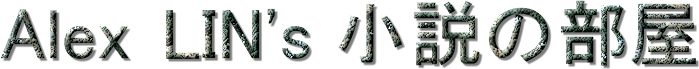告白 其の1
授業が始まった。Andre先生の声が教室に響き、ときどき他のグループからの笑い声が伝わってくる。林と奈々子は授業に集中し、時間が経つのが非常に早かった。林は何回か奈々子の匂いに惑われたけど、今までのようにどきどきしたことは今日はしなかった。
授業が終わり、二人が肩を並んで教室を出た。
「教えて、なぜ大変だったでしょうか?」
「酒本さんが来なかったから、ドア近くのテーブルの女の子と英会話しました」
「あの子が結構可愛いじゃないですか?」
「可愛い?」林が不思議そうに首をかしげて語尾を上げた。「まるでキティちゃんですよ」
「はぁっはぁっはぁっ」奈々子が声を出して笑った。「その通り、私もそう思った」
今まで我慢の反動なのか、奈々子は手が口を押さえながら声を出して笑った。
「全身リボンとレースだらけ、頭までリボンが付いていたよ」林が大げさに両手で女性の服装をなぞった。
ダムが決壊したように、奈々子は片手が口を、もう片手が腹を押さえてさらに高いトンで笑った。通行人の振り返る目線を気にしたか、奈々子は一瞬きつく口を押さえ、笑いを止めらせた。しかし、やはり我慢できず、もう一度爆笑した。
「彼女ってこんなにおもしろいの」林は奈々子が笑い止まるまで待って聞いた。
「彼女もおもしろいけど、林さんの方がもっとおもしろい」笑いすぎたせいか、奈々子が咳をしながらとぎれとぎれに話した。
林は自分が何をしたかを分からなくて、笑って誤魔化していた。
「彼っておもしろいなぁ」奈々子が直感的に思った。
奈々子は相変わらず笑っていた。笑いすぎたせいか、奈々子は歩く気力もなく、二人はゆっくりと歩いていた。通行者から時々不思議そうな目線で二人を見ていたが、二人は気にしなかった。
普段10分ほどでつく外環三条交差点は今日は20分かかった。交差点についた時も、奈々子には笑いの余韻がまだ残っていた。奈々子が笑っている間、林の頭の中には彼女をどう誘うかが一杯だった。
「お茶でもいかかがでしょうか?」林が葛藤した末、勇気を絞って小さい声でゆっくり喋った。
奈々子の笑いが止まり、すぐに返事しなかった。奈々子は目を上げて林を見て、林も気をもんでいて奈々子を見た。二人の目線が合うと、林は顔が赤くなって背け、奈々子は俯いて返事しなかった。奈々子の心の中ではかなり嬉しいけど、突然の誘いの前にどう答えるかを分からなく、微かな不安もあった。奈々子は林の誘いの意味が十分に分かっていて、27才という微妙な年齢に達した奈々子にとっては、目の前の男性をもっと知りたい価値があったと思っていた。
「時間がなければまた今度」林が気まずい空気をかわそうと付け加え、落ち着きがなく、もちろん奈々子を見る余力もなかった。
「いいよ」奈々子がしばらく考え込んだ後、微かな声で返事した。
林は喜んでいる様子は全くなく、すべてのエネルギーを使い果たした抜け殻のように、ただ茫然としていた。逆に奈々子は大勝負が終わってしまったように、大きな荷物が外されたような清々しい気持ちだった。
3分間無言の時間が流れていた。
やっと魂が林の抜け殻に戻り、頭を高速回転させて状況を理解しようとしていた。
「どこへ行くの」奈々子はボーとしていた林に待ちきれず聞いた。
「どこでもいいよ。お好きな店は」林はこれで目一杯だった。
「最近オープンしたミスタードーナツがいかがですか?」奈々子が訪ねてきた。
「もちろんいいよ」林は反対する余地がなかった。
二人が駅方向にもどり、ミスタードーナツに入った。夕飯を食べた林はホットコーヒーだけを注文し、奈々子はアイスコーヒーと2個のドーナツを注文した。林が奈々子の分を払おうとしたが、奈々子に合図で断られ、二人自分の分のお金を払い、席についた。静かな店内に、邪魔とはいえないが、時々となりの席から女子高生のギャル笑いが伝わってくる。
林はやっと自分に戻った。「忙しいところ、誘ってごめん」林は余計なことを言った。
「そんなことはないですよ」奈々子は微笑んでいた。
「先林さんのマネが本当におもしろかったよ」奈々子は言い続けた。先のことを思い出したか、また笑った。
「それを褒められたら立場がないよ」林はそれ以外の答えが見つけなかった。
「林さんが勤めている大手食品会社ってS社でしょうか」奈々子が確認してきた。
林が頭を縦に振り、同意した。
「かなりの大手でしょう。中国の進出の事業を担当しているの」
「それはほめすぎる。今年の4月に入社した新人なので、会社のことは全くわかってないよ。ちなみに配属されてたのが研究部門」
「理系出身?」
「ばりばりの文系、専門は経済学」
「私は経営学部、結構近いね。なぜ研究部門なの」
「会社の配属なので、文句言いようがないよ。でも来年からは中国事業部に移動することになっている」
「それはおめでとう。専門を生かされるかもね」
「大学院で勉強した経済学と会社の経営は全くちがうから」
「大学院ってどこを卒業したの」
「K大の大学院」
「それはすごいね。旧帝大じゃない」
「褒められてもね。その実力が本当にあるか、自分も分からない。だって、今のS社も教授のご推薦があったからだ」
「日本ってそんなもんよ。でもK大の大学院って世間的にやっぱりすごいよ」
「奈々子さんの証券会社ってN社ですか」林は聞き返した。
「そうです」
「IPOとかM&Aってむずかしいじゃない」
「二年前リテール、つまり個人の営業だったが、最近のITバブルでIPOの仕事をメインになった。でもやってるのも本社の手伝いで事務的なことばかり。ITバブルがご存じのように崩壊したから、この先どうなるでしょうね」
奈々子が自分の将来を心配していたか、ちょっと落ち込んだ。
「それで英会話教室ですか?」
「仕事が暇になったから、勉強しなきゃと思って」
「京都は地元でしょうね」林は話題を変えた。
「近くに実家があります」
「大学はどこですか」
「京都のD大の経営学部」
「名門私立じゃない」
「大学の時、あまり勉強してなかったから、結構後悔してるよ。林さんはK大の院卒だから、ちょっと聞きたいが、今の株価指数はどこまでおちる」奈々子の表情に笑いがなく心配そうになっていた。
「僕は予想屋でもないし、株もやってないから、お答えできないと思う」
林は一息して奈々子を見て、奈々子の将来に対する漠然とした心配を感じていた。
「経済学の観点から言えばバブルは付きもの。特に革命的な新しい技術が市場に応用し始めたとき、バブルが非常に発生しやすい。昔、鉄道、自動車、飛行機など一般市場に利用し始めたとき、バブルが起こった。だから、今回のITバブルはその一つじゃないかと思う」
奈々子は林の話をまじめに聞いた。
「バブル発生のメカニズムはどうも人間の脳の構造と関連しているらしい。メタファー理論って聞いたことはないだろう。僕もあまり詳しくないが、簡単に言うと「群衆心理」かな。新しい技術が世に出てきて、それに有望な応用市場が予測されると、正のフィードバックのループに入り、期待自体がさらに高い期待を作り出し、それ自体が株高といった形でバブルが形成する。毎回のバブルに必ずワンフレーズのバズワードがある。日本のバブルなら「Japan as number one」とか、「土地神話」とか、今回のITバブルなら「ニューエコノミックス」とか、「シナジー効果」とか「収穫逓増」とかがあったでしょう。しかし、バブルがすべて悪いではないよ。バブルや恐慌は資本主義の病ではなく、定期的に行なわれる「再起動」って日本人の経済学者宇野弘蔵氏が言ったよ」
奈々子は目を丸くして林の話を聞いた。
「株価がさらに落ちるかどうか分からないけど、これからIT技術をより正確に評価されるだろう。鉄道や自動車のようにIT技術がこれから我々の生活に大きく影響するじゃないかと思う。生活のインフラになるじゃない。ネットワークのインフラ企業は電力会社のように不可欠にはなるけど、あまり稼げないじゃないかと思う」
奈々子は林の答えに正直驚いた。今まで沢山金融レポートをよんだけど、彼の話の方が説得力があると感じた。目の前の男は日本語がもの凄く上手で、帝大出身、大手勤め、英語もそれなりに上手、おまけにおもしろい、と奈々子は本能的に林を株の銘柄のように評価し始めた。ただし、中国人であることに漠然としたリスクを感じていた。林は時々奈々子の反応を見ながら一気に長く話した。証券会社勤めだったか、林の話をほとんど理解したようだ。